レクサスNXは、高級クロスオーバーSUVとして高い評価を得ていますが、一部のオーナー様から「走行中の音がうるさい」「想像していたレクサス車と比べてノイズが大きい」といった声が聞かれることがあります。特に、長距離の高速道路走行や荒れた路面を走る際に、そのノイズが気になり、快適なドライブ体験を損ねていると感じる方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、このレクサスNXのノイズ問題に焦点を当て、なぜ音がうるさいと感じてしまうのか、その具体的な原因を徹底的に分析します。
単に「静かではない」という感想に終わらせず、ノイズの種類(ロードノイズ、エンジン音、風切り音など)ごとに発生メカニズムを深く解説し、さらにプロの視点から、効果的かつ実践的な静音化の対策と具体的なDIYの方法を5つのコツとして紹介します。この記事を読み終える頃には、ご自身のNXのノイズの原因が特定でき、そしてそのノイズを大幅に軽減し、より快適で上質なレクサス本来の静粛性を手に入れるための具体的な道筋が見えているはずです。
【この記事で分かること】
- レクサスNXで発生しやすいノイズの具体的な種類とその発生源
- 年式やグレードによってノイズ傾向がどのように異なるのか
- 静音性に優れたタイヤ選びや制振材・吸音材を使ったDIY対策
- ウェザーストリップ強化など、プロが推奨する風切り音の低減テクニック
- ディーラーオプションやカーオーディオ調整でノイズを軽減する方法
レクサスNXのノイズがうるさいと感じる原因とは?
レクサスというブランドは、世界でもトップクラスの静粛性が約束されているイメージが強いですが、NXクラスのクロスオーバーSUVは、セダンやフラッグシップモデルとは異なる構造的な課題を抱えています。車高が高いこと、そしてタイヤやサスペンションが路面からの入力をより直接的に受け止めやすい設計であることから、特定のノイズが車室内に侵入しやすくなります。
特に、プラットフォームを共有する車種との比較や、先代モデルからの進化を期待していたオーナー様にとっては、その静粛性が期待値に届かないと感じられるケースも少なくありません。
ノイズは単なる不快音ではなく、疲労の原因にもなります。そのため、快適なドライブを維持するためには、ノイズがどこから、どのようなメカニズムで発生しているのかを正確に理解することが、静音化対策の第一歩となります。ここでは、レクサスNXのノイズがうるさいと感じられる主要な原因を、一つひとつ掘り下げて分析していきます。ノイズの種類ごとに適した対策が異なりますから、ご自身のNXで最も気になる音の種類と照らし合わせて確認してみてください。
タイヤからのロードノイズが大きい理由と対策
ロードノイズは、レクサスNXのノイズの中でも特に多くのオーナー様が「うるさい」と感じる原因の筆頭です。これは、タイヤが路面と接触する際に発生する振動や空気のポンピング音が、ホイールハウスやサスペンションを経由して車室内に伝わることで生じます。NXのようなSUVタイプの車は、セダンに比べてタイヤハウスと車室内の距離が近く、また採用されるタイヤのサイズが大きく幅広になる傾向があるため、必然的にロードノイズの発生源が大きくなります。
ロードノイズの発生メカニズムの詳細
ロードノイズには主に三つの種類があります。
パターンノイズ
タイヤのトレッドパターン(溝)が路面と接触・離脱する際に、溝内の空気が圧縮・開放されることで生じる音です。特に速度が上がると「コーッ」「ゴーッ」といった周期的な音として聞こえやすくなります。
共鳴ノイズ
タイヤやホイール、そしてサスペンションが路面からの微細な振動を受け取り、それが車体全体のパネルを振動させて発生するノイズです。特定の速度域や路面の荒れ具合によって「ブーン」という低い唸り音として共振することがあります。
空洞共鳴音(こもり音)
タイヤ内の空洞が共振することで発生するノイズで、低周波の「モォー」というこもった音として車室内に響きます。この低周波ノイズは耳には聞こえにくいものの、不快感や疲労につながりやすいと指摘されています。
これらのノイズの中でも、NXでは特に共鳴ノイズや空洞共鳴音が目立ちやすい傾向にあります。これは、SUV特有の剛性が高い車体構造と、大径タイヤの組み合わせによるものです。対策としては、タイヤハウス内側への制振材や吸音材の施工が有効です。
制振材でパネルの振動を抑え、吸音材でタイヤから発生する音を吸収することで、ノイズの車室内への侵入を大幅に低減できます。また、後述する静音性に特化したタイヤへの交換も、ノイズの発生源そのものを抑える最も根本的な対策の一つとなります。
| ロードノイズの種類 | 主な発生源 | 聞こえやすい音の特徴 | 対策の方向性 |
| パターンノイズ | タイヤの溝と路面との摩擦・空気の圧縮 | 「コーッ」「ゴーッ」という周期音 | 静音タイヤへの交換、タイヤハウスへの吸音材施工 |
| 共鳴ノイズ | 車体パネルやサスペンションの振動 | 「ブーン」「モォー」という低い唸り音 | 車体パネル(フロア、ドア)への制振材施工 |
| 空洞共鳴音 | タイヤ内部の空気の共振 | 低周波の「ウオーン」というこもり音 | タイヤ内部にスポンジを仕込むタイプのタイヤ、制振材の追加 |
エンジン音がうるさいと感じる走行シーンとは?
レクサスNXのエンジン音は、セダンモデルと比較して、特に急加速時や高負荷運転時に車室内に侵入しやすい特性を持っています。レクサスNXにはガソリンモデルとハイブリッドモデル(NX350hやNX450h+)がありますが、どちらのパワートレインにおいても、特定の走行シーンでエンジン音が「うるさい」と感じる瞬間があります。
駆動方式や走行モードとノイズレベルの関係
ガソリンモデル(NX350など)
自然吸気エンジンからターボエンジンへと進化しており、特にターボチャージャーが作動し始める中回転域から高回転域にかけて、エンジン音が増大します。日本の交通環境では、料金所からの合流や高速道路での追い越しなど、瞬間的に大きなトルクを必要とするシーンでエンジン回転数が急激に上昇し、その結果、エンジンノイズが車室内に強く響きます。
ハイブリッドモデル(NX350h, NX450h+)
通常は静かなEV走行が可能ですが、バッテリー残量が少ない時や、急な坂道、高速道路でアクセルを深く踏み込んだ時に、エンジンが始動し、その音が際立ちます。ハイブリッド車特有の現象として、走行速度とエンジン回転数が一致しない「ラバーバンドフィール」があるため、エンジンの唸り音が不自然に長く続き、ノイズとして耳に残りやすくなります。
これは、エンジンの回転数を上げて発電やバッテリー充電を行い、駆動をモーターに頼るというシステム構造上の特性によるものです。
また、スポーツモードを選択した場合、エンジンレスポンスの向上に伴い、意図的にエンジン回転数が高めに維持されるため、ノイズも増加します。しかし、これは運転の楽しさを演出する「サウンド」としての側面もあり、一概に「うるさい」とは言い切れない部分もありますが、静粛性を重視するレクサスオーナーにとっては気になるポイントとなり得ます。
対策としては、エンジンルームとダッシュパネル周辺への遮音・吸音対策が最も効果的です。特にダッシュパネル裏側への制振材や吸音材の施工は、エンジンからの直接的な音の侵入を防ぐ上で非常に重要となります。
| 走行シーン | ノイズ発生の原因 | ノイズの特徴 | 対策の優先度 |
| 高速道路合流時の急加速 | エンジン高回転の持続 | 鋭い唸り音、高周波ノイズ | エンジンルーム、ダッシュパネルの遮音 |
| 坂道走行時(HV車) | エンジン始動と発電のための高回転 | 不自然に続く「モォー」というこもり音 | ダッシュパネル、フロアの制振・遮音 |
| アイドリング時(ガソリン車) | エンジン本体の振動、燃料噴射音 | 低い振動音、メカニカルノイズ | ボンネット裏の吸音材、バルクヘッドの制振 |
参照元:日本自動車工業会(JAMA)
ドアやフロアから入る風切り音の原因と防ぎ方
高速走行時や強風の中での走行において、「ヒューヒュー」という高周波の音や「ゴー」という低い音がドアミラー付近やドアの隙間から聞こえることがあります。これが風切り音、または風騒音と呼ばれるものです。レクサスNXのような車高の高いSUVは、セダンと比較して前面投影面積が大きくなる傾向があり、空気抵抗が増すため、風切り音の対策がより重要になります。
風切り音が発生するメカニズム
風切り音の主な発生箇所は、空気の流れが乱れる部分です。
ドアミラー周辺
走行風がドアミラーの付け根や形状に当たって渦を巻き、その乱れた空気がドアガラスやボディ表面を通過する際にノイズが発生します。
ドアの合わせ目(ウェザーストリップ部)
ドアとボディの間の密閉性を保つゴムパッキン(ウェザーストリップ)の劣化や、密着性の不足、または設計上のわずかな隙間が原因で、空気がその隙間を高速で通過する際にノイズが生じます。特に速度が上がるほど、このノイズは顕著になります。
ピラーやルーフの継ぎ目
Aピラー(フロントガラス横の柱)やルーフとサイドガラスの境界線も、空気の流れが急激に変化する場所であり、風切り音の原因となり得ます。
風切り音を防ぐための対策は、これらのノイズ発生源を特定し、空気の流れをスムーズにするか、隙間を完全に塞ぐかの二つに大別されます。最も効果的なのは、ウェザーストリップの強化です。純正のウェザーストリップの上から、さらに密度の高いゴムモールを追加したり、D型やP型のシール材を貼り付けることで、ドアの密閉性を高め、風の侵入経路を物理的に遮断します。
また、ドアミラーの根元部分に小さな整流効果のあるスポイラーのようなパーツ(社外品で多く販売されています)を追加することも、空気の流れを整え、ノイズの発生を抑える効果が期待できます。これらの対策は比較的安価でDIYがしやすく、すぐに効果を実感しやすい対策としても知られています。高周波の風切り音は特に耳障りであるため、まずはウェザーストリップの点検と強化から始めることをお勧めします。
| 風切り音の発生箇所 | 音の特徴 | 推奨される対策 | 対策の効果 |
| ドアミラー根元・付け根 | 「ヒューヒュー」という高周波音 | 整流パーツの追加、ミラー裏の制振材 | 風の乱れを抑え、ノイズの発生を抑制 |
| ドアの合わせ目(ウェザーストリップ) | 「ゴー」という低い音、または「スー」という漏れ音 | 強化モールやシール材の追加(P型、D型) | ドアの密閉性を向上させ、風の侵入を防ぐ |
| Aピラー周辺 | 走行風による不規則なノイズ | Aピラー内側への吸音材施工、モール追加 | 車体への風の当たり方を調整し、遮音効果を高める |
参照元:カーエアロダイナミクス研究室
ハイブリッドモデル特有のモーター音が気になるケース
レクサスNXのハイブリッドモデル(NX350h、NX450h+)は、静粛性が高いことが最大の魅力の一つですが、EV走行中に限っては、ガソリン車とは異なる種類のノイズが気になり始めることがあります。それは、モーターの駆動音やインバーターが発する電子音です。ガソリンエンジンが停止しているため、普段は聞こえないこれらのノイズが際立ち、敏感なオーナー様にとっては「うるさい」と感じる原因になります。
EV走行時に特有のノイズ
モーター駆動音
電気モーターが回転する際に発生する「キーン」あるいは「ヒュイーン」という高周波のノイズです。特に低速域での加速時や回生ブレーキ作動時に発生しやすく、車速に応じて周波数が変化するのが特徴です。
インバーターの電子音
バッテリーの直流電力を交流電力に変換するインバーター(電力変換装置)から発生する「ジー」あるいは「チー」という電子的なノイズです。このノイズは、走行状態にかかわらず持続的に聞こえることがあり、ノイズキャンセリング技術がないと車室内に侵入しやすい特性を持っています。
これらのノイズが目立つのは、エンジン音という大きなノイズが消えることによって、相対的に小さかったモーター系ノイズが「浮き上がってくる」ためです。レクサスは、これらのノイズを低減するために、遮音材や吸音材を効果的に配置していますが、完全に消すことは難しく、特に車体の床下や後部座席下に配置されるバッテリーやインバーターユニットからの振動・音が、フロアパネルを通して車室内に伝わってしまうことがあります。
対策としては、フロアパネル全体の制振・吸音対策が効果的です。特に、後部座席の足元やトランクルーム下(バッテリーやインバーターが近い場所)に制振材を貼り付け、その上に吸音材を敷くことで、ユニットからの振動伝達とノイズの侵入を抑制することができます。
また、これらのノイズは高周波であるため、吸音性の高い素材(厚手のフェルトやウレタンフォーム)を効果的に使用することがポイントとなります。プロの施工では、これらのユニット周辺の防音処理が重要視されます。
| ノイズの種類 | 発生源 | 聞こえやすい音の特徴 | 対策箇所 |
| モーター駆動音 | 駆動用モーター | 「キーン」「ヒュイーン」という高周波音 | フロアパネル、モーター周辺のバルクヘッド |
| インバーター電子音 | 電力制御ユニット(インバーター) | 「ジー」「チー」という持続的な電子音 | 後部座席下、トランクルーム下の制振・吸音 |
| 低速警告音(VSP) | 外部スピーカー | 歩行者への注意を促す人工音 | (車室内には直接関係ないが、運転者には聞こえる) |
参照元:防音・制振技術協会(JNVH)
雨天や高速道路走行でノイズが増える理由
レクサスNXのノイズは、特定の環境下、特に雨天時や高速道路での走行時に顕著に増大する傾向があります。これは、単に速度が上がるからというだけでなく、物理的な現象や路面とタイヤの相互作用が変化することが主な原因です。これらの条件でノイズが増える理由を理解すれば、その状況に合わせた適切な対策を講じることができます。
速度と環境によるノイズの複合的な影響
高速道路走行によるノイズの増大
車速が二倍になると、空気抵抗は約四倍に増加します。これに伴い、風切り音も急激に増大します。時速100kmを超えると、ロードノイズよりも風切り音が支配的なノイズ源となることが一般的です。また、高速道路では路面舗装の種類(アスファルトの粒度やコンクリート)もノイズに大きく影響し、特に目地の多いコンクリート路面では、タイヤとの衝撃が共振ノイズを増幅させます。
雨天走行によるノイズの増大
雨が降ると、以下の二つのノイズが発生し、静粛性を低下させます。
水しぶき音(水切り音)
タイヤが路面の水を蹴り上げる際に、水がタイヤハウスや車体下部に叩きつけられて発生する音です。これは「バシャバシャ」という不規則なノイズとして聞こえ、特にタイヤハウス周辺の防音対策が不十分な場合に目立ちます。
ハイドロプレーニング現象の初期段階
水膜の上をタイヤが滑ることで、摩擦音とは異なる「シャー」という音がタイヤから発生します。これは、タイヤの排水性能を超えた走行速度で生じ、ロードノイズに重なる形で聞こえます。
これらの複合的なノイズを低減するには、まず高速域で支配的になる風切り音対策(ウェザーストリップ強化)を徹底することです。次に、雨天時の対策として、タイヤハウスのインナーライナー(内側のカバー)を防音・吸音性の高い素材(たとえば、厚手のフェルトやブチルゴムシート)に交換、または追加で貼り付けるDIYが非常に有効です。これにより、水滴や小石の跳ね上げ音を大幅に軽減することができます。
| 走行条件 | ノイズ増加の主な原因 | 発生するノイズの種類 | 対策の焦点 |
| 高速道路走行 | 空気抵抗の急増、路面との共振 | 風切り音(ヒュー)、ロードノイズ(唸り) | ドア周辺の密閉強化、フロアの制振 |
| 雨天走行 | 水の跳ね上げ、ハイドロプレーニング | 水切り音(バシャ)、滑走音(シャー) | タイヤハウス、フェンダー内の吸音・遮音 |
| 荒れた路面 | 不規則な衝撃、サスペンションの振動 | 低周波の「ドン」「ゴツ」という衝撃音 | フロア・シート下の制振材、サスペンションマウントの防振 |
参照元:タイヤ技術研究所
防音材が足りない?静音パッケージ未装備車の特徴
レクサスNXの標準仕様車と、上級グレードや特別装備車に設定される静音パッケージ装備車とでは、使用されている防音・遮音材の量や質に違いがある場合があります。特にコストを抑えた仕様の車両では、目に見えない部分での防音対策が簡略化されていることがあり、これがノイズレベルの違いとなって現れます。
静音パッケージがもたらす効果
静音パッケージやそれに類するオプションが装備されている車両は、以下の部分で標準車との差が見られます。
二重遮音ガラス(アコースティックガラス)
フロントドアガラスやフロントガラスに、防音効果を高める特殊な中間膜を挟んだ二重構造のガラスが採用されていることがあります。これにより、車外からの騒音、特に高周波の風切り音や対向車の音を大幅にカットする効果があります。
追加の吸音材・制振材の配置
ドア内部、フロアパネルの裏側、ルーフ内側、そしてトランクルームのサイドパネルなどに、厚手の吸音材や高密度な制振シートが追加で貼り付けられています。これにより、ロードノイズの共振や外部からの騒音侵入を防ぎます。
タイヤハウス内のインナーライナー
静音性の高いインナーライナーには、フェルト素材や繊維系の吸音材が一体化されていることが多く、標準車の樹脂製ライナーと比較して、タイヤからのノイズを吸収する能力が格段に高くなります。
標準仕様やベースグレードのレクサスNXを所有されているオーナー様でノイズが気になる場合は、この「静音パッケージが足りない部分」を後付けで補強するDIY対策が最も費用対効果が高いと言えます。特に、静音パッケージで採用されることの多い、ドアパネル内側やルーフ裏側への吸音材の追加は、広い面積をカバーできるため、体感できる効果が大きいでしょう。
中古車で購入された場合や、オプション装備を気にせず購入された方は、一度ご自身の車のガラスや内装材の仕様を確認してみることを推奨します。
| 対策部位 | 静音パッケージ装備車 | 標準仕様車 | 後付け対策のポイント |
| ドアガラス | 二重遮音ガラス(アコースティックガラス) | 単板ガラスまたは標準ガラス | ドア内部への制振・吸音材の追加 |
| フロア/ルーフ | 厚手の吸音材、高密度制振シート | 軽量な制振シートのみ、吸音材の省略 | フロアマット下に遮音材、ルーフ裏に吸音材 |
| タイヤハウス | フェルト材一体型インナーライナー | 樹脂製または薄手のインナーライナー | インナーライナーの裏側への吸音材貼り付け |
参照元:車両NVHマテリアル進化レポート
レクサスNXの年式・グレード別に異なるノイズ傾向
レクサスNXは、フルモデルチェンジやマイナーチェンジの度に、プラットフォームやボディ剛性、そして静粛性へのアプローチが進化しています。そのため、所有されているNXの年式やグレードによって、ノイズの発生傾向や気になる音の種類が異なる場合があります。ご自身のNXがどの世代に属し、どのような特性を持っているのかを知ることは、効果的なノイズ対策を行う上で不可欠です。
世代ごとの設計思想と静音性の違い
初代NX(2014年~2021年)
初代NXは、レクサスとして初めてこのセグメントに投入されたモデルであり、静粛性については当時のセダンモデルほどの徹底した対策はされていませんでした。特に初期モデルでは、ロードノイズやエンジン音が比較的車室内に侵入しやすい傾向にあります。対策としては、フロアやルーフへの本格的な制振・吸音DIYが大きな効果をもたらします。
二代目NX(2021年~)
現行型NXは、新世代のプラットフォーム(TNGA-K)を採用し、ボディ剛性が大幅に向上しました。これにより、車体自体の共振ノイズは低減されましたが、その反面、タイヤからのロードノイズやサスペンションからの突き上げ音が、よりダイレクトに車室内に伝わる傾向も見られます。静音対策の重点は、初代が「音の侵入を防ぐ」ことにあったのに対し、現行型は「振動の伝達を遮断する」ことに移っていると言えます。
グレード別のノイズ傾向
F SPORTグレード:専用のサスペンションや大径ホイール、パフォーマンスダンパーなどが装備されるため、走行性能は向上しますが、路面からの入力がダイレクトになり、結果としてロードノイズや路面からの突き上げ音が強調されやすい傾向があります。
標準・version Lグレード:比較的乗り心地重視のセッティングであり、タイヤサイズも標準的であるため、F SPORTと比較してノイズは穏やかです。しかし、豪華装備のversion Lであっても、静音パッケージがオプションの場合、ガラス周りなどの防音対策は標準仕様と変わらないため、風切り音が気になることがあります。
ご自身のNXの特性に合わせて対策を絞り込むことがノイズ改善への近道です。例えば、初代オーナー様はフロア・ルーフの面全体を、現行型オーナー様はタイヤハウスやサスペンション周辺のピンポイントな制振を強化するといったアプローチが考えられます。
| 年式・世代 | ノイズの主な傾向 | 対策の主な焦点 |
| 初代NX (2014-2021) | 全体的な遮音性の低さ、エンジン音の侵入 | ドア、ルーフ、フロアへの吸音材による広範囲の対策 |
| 現行型NX (2021-) | ロードノイズ・突き上げ音のダイレクトな伝達 | タイヤハウス、フロアパネル、サスペンション周辺の制振強化 |
| F SPORT | 大径タイヤによるロードノイズ、硬い足回りによる共振 | 静音タイヤへの交換、制振材による振動対策 |
| version L | 風切り音(静音ガラス非装着の場合) | ウェザーストリップ強化、Aピラー周辺の対策 |
参照元:自動車評論家 専門コラム
レクサスNXの音がうるさいときに試したい静音化のコツ5選

レクサスNXのノイズの原因が特定できたところで、次に気になるのは「どうすれば静かになるのか」という具体的な方法でしょう。闇雲に防音材を貼り付けるだけでは、期待した効果が得られないだけでなく、車両重量が増加して燃費や走行性能に影響が出る可能性もあります。プロのライターとして、私は最も効果が高く、コストパフォーマンスにも優れた静音化のコツを5つに絞り込みました。
これらの対策は、ノイズの発生源を断つ「発生抑制」、車内への音の侵入を防ぐ「遮音」、そして車内で反射・増幅する音を吸収する「吸音・制振」という三つの柱に基づいています。愛車NXをより上質な空間に変えるために、ぜひ以下の対策を参考にしてください。静音化は、運転の疲労を軽減し、カーオーディオの音質向上にもつながる、快適なカーライフへの投資です。
【以下で分かること】
- ロードノイズを根本から抑える静音タイヤの選び方と効果
- DIYで効果を最大化するための制振材と吸音材の正しい使い方
- コストをかけずに風切り音を大幅に軽減する密閉強化テクニック
- エンジンルーム内のノイズを抑制するプロ仕様の遮音対策
- プロの手によるオプション施工で得られる確実な静粛性の向上
タイヤ交換でノイズを減らす!おすすめ静音タイヤとは
レクサスNXの静音化において、最も効果を実感しやすく、かつ根本的な対策となるのがタイヤ交換です。ロードノイズの主要な発生源であるタイヤそのものを静音設計のものに交換することで、ノイズの発生量を大幅に抑えることができます。特に、パターンノイズや空洞共鳴音(こもり音)に対しては、タイヤの構造が直接的に影響するため、その効果は絶大です。
静音タイヤの構造と選び方
静音タイヤは、一般的なタイヤと比較して、以下の三つの工夫が施されています。
低ノイズパターン
トレッドパターン(溝)の配列を不規則にすることで、パターンノイズの周波数を分散させ、耳に届く音を和らげます。この設計により、「コーッ」「ゴーッ」といった周期的なノイズが大幅に低減されます。
吸音スポンジの内蔵
タイヤ内部の空洞にポリウレタンなどの吸音スポンジを貼り付けることで、走行中にタイヤ内部で発生する空洞共鳴音(こもり音)を吸収します。これが低周波ノイズによる不快感や疲労の軽減に最も効果を発揮します。
ソフトなコンパウンドと柔軟な構造
路面からの衝撃を吸収しやすいよう、ゴムのコンパウンド(組成)を柔らかくしたり、サイドウォール(側面)を柔軟に設計しています。これにより、路面との接触音や振動の伝達を和らげる効果があります。
NXにおすすめの静音タイヤとしては、ブリヂストンの「REGNO GR-XⅡ」やヨコハマタイヤの「ADVAN dB V552」、ダンロップの「VEURO VE304」といったプレミアムコンフォートタイヤが挙げられます。これらのタイヤは、高い静粛性だけでなく、乗り心地やウェット性能も両立させているため、レクサスNXの高級感を損なうことなく静音化を実現できます。
タイヤを選ぶ際は、静粛性の指標だけでなく、NXの重量に見合ったロードインデックス(耐荷重性能)を持っているかを必ず確認してください。
| 静音タイヤの機能 | 対策できるノイズの種類 | 主な効果 |
| 低ノイズトレッドパターン | パターンノイズ、高周波ノイズ | 周期的な「ゴー」という音を分散・低減 |
| 吸音スポンジ(特殊吸音層) | 空洞共鳴音、低周波ノイズ | 低い「モォー」というこもり音を大幅に抑制 |
| ソフトなコンパウンド・構造 | ロードノイズ、突き上げ時の衝撃音 | 走行中の微細な振動を吸収し、快適性を向上 |
参照元:タイヤ技術研究所
ドアや床下への制振材・吸音材の追加方法
DIYでの静音化対策の核となるのが、制振材と吸音材の適切な施工です。特に、ドアパネルと床下(フロアパネル)は、ロードノイズや風切り音、エンジン音の振動が車室内に伝わる主要な経路であり、この二箇所への対策を徹底することで、体感的な静粛性を大きく向上させることができます。
制振と吸音の役割と施工のポイント
制振材の役割
制振材(デッドニングシート)は、主にブチルゴムやアスファルト系樹脂でできており、パネルの振動を抑えることを目的としています。ドアパネルやフロアパネルに貼り付けることで、走行中のロードノイズやエンジンの振動によってパネル自体が共振し、音を増幅させるのを防ぎます。施工の際は、パネルの最も振動している箇所(叩いてみて響く場所)に、全体の70%程度を目安に隙間なく貼り付けることが重要です。
吸音材の役割
吸音材は、主にウレタンフォームやフェルト素材でできており、車室内に侵入した音を熱エネルギーに変換して消滅させることを目的としています。ドアパネルの内側(制振材の上)や、フロアカーペットの下、ルーフ内側などに配置することで、反射音や残響音を抑え、音響的な静粛性を向上させます。
施工箇所と手順
フロアパネル(床下)への施工
シートや内装材を外し、鉄板が露出したフロア全体に制振材を貼り付けます。特にタイヤハウスの真上やシートレールの下など、振動が伝わりやすい部分を重点的に施工します。その後、その上に遮音性の高い素材(厚手のゴムシートなど)と吸音材を重ねて敷き詰めます。この対策は、低周波のロードノイズや排気音のこもり音に対して極めて有効です。
ドアパネルへの施工
ドアの内張りを外し、ドアアウターパネル(車外側の鉄板)に制振材を貼り付け、共振を抑えます。その上で、サービスホール(点検用の穴)を塞ぐようにインナーパネル全体に制振材を貼り付け、最後に吸音材をドア内部に配置します。これにより、風切り音や外部騒音の侵入を防ぎ、同時にカーオーディオの音質も劇的に改善されます。
注意点として、制振材を貼りすぎると車両重量が増加しすぎたり、ドアの内張りが元に戻せなくなったりする可能性があるため、適切な厚さと量を見極めることがプロのテクニックとなります。
| 対策箇所 | 対策の目的 | 推奨材料の種類 | 効果 |
| ドアアウターパネル | パネルの共振抑制、風切り音の遮断 | ブチルゴム系制振シート | 外部騒音の侵入を抑え、オーディオ音質を改善 |
| フロアパネル | ロードノイズ、排気音の振動伝達遮断 | 厚手の制振材、遮音シート | 低周波のこもり音と振動を大幅に軽減 |
| ルーフパネル | 雨音の低減、車内音の吸音 | 軽量吸音材(ウレタンフォームなど) | 雨天時の快適性向上、音響空間の改善 |
参照元:防音・制振技術協会(JNVH)
ウェザーストリップの強化で風切り音を低減するコツ
風切り音は、高速走行時のノイズの主要因でありながら、比較的安価で簡単にDIY対策ができるノイズです。その鍵となるのが、ドア周りの密閉性を高めるウェザーストリップ(ゴムパッキン)の強化です。レクサスNXのドアは精密に設計されていますが、走行時の風圧や経年劣化により、わずかな隙間が生じ、そこから風切り音が発生します。
強化用ゴムモールの種類と効果的な貼り方
ウェザーストリップの強化には、主に社外品のゴムモールやシール材を使用します。
D型ゴムモール
断面がアルファベットの「D」の形をしたモールです。主にドアとボディの間のメインのウェザーストリップの補助として、ドアの縁やボディ側の隙間に貼り付けます。これにより、ドアを閉めた際の密着性が向上し、風の侵入経路を物理的に塞ぎます。
P型ゴムモール
断面が「P」の形をしており、主にドアの開口部の内側や、ボンネット、トランクリッドの隙間を埋めるのに使われます。D型と組み合わせて使用することで、多層的な密閉構造を作り出し、風切り音を効果的に遮断します。
ドアエッジプロテクター型のモール
ドアの縦の縁(AピラーやBピラーに接する部分)に貼り付け、ドア閉鎖時の密着度を上げることで、特にAピラー付近で発生しやすい高速域の風切り音を軽減します。
効果的な貼り方のコツ
脱脂作業の徹底
モールを貼り付ける前に、貼り付け面をシリコンオフやアルコールなどで徹底的に脱脂することが重要です。油分が残っていると、すぐに剥がれてしまい、効果が持続しません。
貼り付け位置の微調整
モールを貼り付けたら、一度ドアを閉めて、モールが均等に圧縮されているかを確認します。隙間が残っている部分がないか、ドアの開閉に支障がないかを確認しながら、最適な位置を見極める必要があります。特に、ドアのロック部分周辺は、ノイズの侵入源になりやすいため、重点的に密閉度を高めましょう。
このウェザーストリップ強化は、風切り音だけでなく、外部の騒音(救急車のサイレンや対向車の音など)の侵入も同時に防ぐため、車室内の静粛性を総合的に向上させる非常にコストパフォーマンスの高い対策と言えます。
| ゴムモールの種類 | 主な断面形状 | 対策の主な焦点 | 期待される効果 |
| D型モール | D字型 | ドアとボディ間の隙間の物理的な遮断 | 風切り音の低減、外部騒音の侵断 |
| P型モール | P字型 | ボンネット、トランクリッド、ドア内側の隙間充填 | エンジンノイズ、排気音の侵入抑制 |
| ドアエッジプロテクター型 | L字型またはU字型 | ドアの縦方向の密着性向上 | Aピラー周辺からの高速域ノイズの軽減 |
参照元:カー用品技術部
エンジンルーム内の遮音対策でアイドリング音を軽減
レクサスNXのノイズの中で、特にアイドリングストップが解除された瞬間や、信号待ちのアイドリング中に気になるのがエンジン音です。エンジンルーム内の遮音対策は、このエンジンからの透過音と振動を直接的に遮断し、車室内への侵入を抑えることを目的としています。この対策には、ボンネット裏とダッシュパネル周辺の二つのエリアが重要になります。
ボンネット裏とダッシュパネルへの施工
ボンネット裏の吸音材追加
多くの車両には、ボンネットの裏側に純正のインシュレーター(吸音材)が装着されていますが、その材質や厚さはグレードによって異なります。市販の高密度な吸音シートや耐熱性のある制振材を、純正インシュレーターの上から追加で貼り付けることで、エンジンから上方へ放出される音を吸収し、エンジン音を大幅に軽減できます。
特に、ディーゼル車や直噴ガソリンエンジンの「カチカチ」といったメカニカルノイズに対して有効です。
ダッシュパネル(バルクヘッド)への対策
ダッシュパネル(エンジンルームと車室を隔てる隔壁)は、エンジン音と振動が最も直接的に車室内に伝わる場所です。この部分への対策は、フロアやドアよりも難易度が高く、プロの施工領域となることが多いですが、効果は最も高いと言えます。DIYで行う場合は、エンジンルーム側から見える範囲で、遮音性の高いアルミ付きの制振シートを貼り付け、その上に防音性の高い遮音材を設置します。
インナー側の対策
車室内側のダッシュパネル(運転席の足元など)の内装材を剥がし、制振材と遮音材を貼り付ける方法です。これは作業範囲が広いため大変ですが、エンジンからの透過音を最も効果的に遮断できます。この対策は、エンジン音だけでなく、ATの作動音や排気音などの低周波ノイズにも効果を発揮します。
安全上の注意点として、エンジンルーム内に施工する材料は、必ず耐熱性・難燃性の高い自動車専用品を選び、エンジンの熱源や可動部分(ベルトなど)に触れないように細心の注意を払って施工してください。また、エンジンルームのカバー類を外して作業する場合、再取り付け時にネジの締め忘れなどがないよう、慎重に行う必要があります。
| 対策箇所 | ノイズの種類 | 推奨材料 | 施工時の注意点 |
| ボンネット裏 | メカニカルノイズ、上方への音の放出 | 耐熱吸音シート、アルミ付き制振材 | 可動部を避け、耐熱性を確保する |
| ダッシュパネル(エンジンルーム側) | 透過音、エンジン本体の振動 | 高密度制振シート、遮音材 | 難易度高、熱源から離して確実に貼り付ける |
| ダッシュパネル(車室内側) | 透過音、低周波の振動 | 制振材、遮音性の高い吸音マット | 大がかりな内装の脱着が必要、効果は最も高い |
参照元:自動車整備技術ガイド
ディーラーでできる静音オプションやサービス内容
DIYでの静音化には限界がある、あるいは作業に自信がないというオーナー様にとって、最も確実で安心できるのが、レクサスディーラーや専門業者による静音オプションやサービスを利用することです。ディーラーで提供されるオプションは、車両の設計を熟知した上で施工されるため、安全性や保証面でも安心感があります。
純正オプションとプロによる施工のメリット
純正防音パッケージの後付け
新車購入時に静音パッケージ(アコースティックガラスや追加吸音材など)を選択しなかった場合でも、一部の部品は後付けが可能な場合があります。例えば、静音性能の高い純正フロアマットや、タイヤハウス内の防音インナーライナーなどは、ディーラーで部品を取り寄せて交換してもらうことができます。
プロによる防錆・防音処理
レクサスディーラーでは、アンダーコート(車体下部コーティング)の一環として、防錆だけでなく防音効果を兼ね備えた特殊なコーティング剤を施工している場合があります。車体下部に厚く塗布することで、ロードノイズや小石の跳ね上げ音を軽減する効果があります。
専門業者によるデッドニング施工
ディーラーではなく、カーオーディオ専門店やデッドニング専門のプロショップに依頼する方法も非常に有効です。これらの専門店は、高性能な制振材や吸音材を豊富に取り揃えており、長年の経験からレクサスNXのノイズの弱点を熟知しています。
特に、ダッシュパネル裏側やルーフなど、DIYでは難しい箇所への徹底した施工は、プロならではの技術です。費用は高くなりますが、確実な静粛性の向上と、オーディオ音質の劇的な改善を同時に実現できます。
プロに依頼する最大のメリットは、材料の選定ミスや施工の失敗がなく、手間をかけずに最大の効果が得られることです。予算と求める静粛性のレベルに合わせて、ディーラーオプションの利用と、専門業者へのオーダーメイド施工を検討してみてください。
| サービスの種類 | 施工箇所 | 特徴とメリット | 費用の目安(概算) |
| 純正防音フロアマット | フロア全体 | 車両への適合性が完璧、低周波ノイズの吸音 | 3万円~8万円 |
| アンダーコート(防音タイプ) | 車体下部、タイヤハウス | 防錆効果とロードノイズの軽減を両立 | 5万円~15万円 |
| プロショップによるフルデッドニング | ドア、フロア、ルーフ、ダッシュパネル | 最高の静粛性、音響性能の向上 | 20万円~50万円 |
参照元:サウンドマスターズ
カーオーディオの調整で体感ノイズを軽減する方法
物理的な静音化対策がノイズの侵入を「防ぐ」ことであるのに対し、カーオーディオの調整は、車室内の音響空間を操作し、ノイズの「不快感」を軽減することを目的とした間接的な対策です。レクサスNXに搭載されている高級オーディオシステム(マークレビンソンなど)の機能を最大限に活用することで、ノイズが気になりにくい環境を作り出すことができます。
イコライザー調整とノイズキャンセリング機能の活用
イコライザー(EQ)の調整
ノイズの中でも特に耳障りに感じるのは、特定の周波数帯の音です。
- 低周波ノイズ(ロードノイズのこもり音、排気音)
「ブーン」「モォー」といった低い音は、80Hz以下の帯域に集中します。この帯域の音量をわずかに下げる(数デシベル)ことで、不快感を軽減できます。ただし、下げすぎると音楽のベース音まで弱くなるため注意が必要です。 - 高周波ノイズ(風切り音、モーター音)
「ヒュー」「キーン」といった高い音は、8kHz以上の帯域に集中します。この帯域の音量を調整することで、耳障りなノイズを和らげることができます。
リスニングポジションの調整
レクサスのオーディオシステムには、運転席や助手席など、特定の座席に合わせて音響を最適化する機能が搭載されていることがあります。この機能を活用することで、ドライバーの耳元でのノイズレベルを最も低く抑えることができます。
ノイズキャンセリング(ANC)機能
一部の高級オーディオシステムや新型NXのグレードには、ロードノイズやエンジン音といった特定のノイズをマイクで拾い、それと逆位相の音波をスピーカーから流すことで打ち消す「アクティブノイズコントロール(ANC)」が搭載されています。この機能が搭載されている場合は、システムが正しく作動しているかを確認し、その効果を最大限に享受することが重要です。
また、ノイズ対策を施した後にオーディオを調整することで、その効果はさらに明確になります。制振・吸音材でノイズの絶対量を減らし、残ったノイズをオーディオの調整でさらに目立たなくするというアプローチが、最も快適な車内空間を作り出すための秘訣です。音楽を楽しむための調整だけでなく、ノイズを軽減するための「音響的ノイズコントロール」としてカーオーディオを捉え直してみてください。
| オーディオ調整項目 | ノイズの種類 | 調整の目的 | 期待される効果 |
| イコライザー(低域80Hz以下) | 低周波のロードノイズ、こもり音 | ノイズが集中する帯域をピンポイントで下げる | 不快な唸り音による疲労の軽減 |
| イコライザー(高域8kHz以上) | 風切り音、モーター音 | 耳障りな高音域を穏やかにする | 「ヒュー」「キーン」という鋭い音の和らげ |
| アクティブノイズコントロール(ANC) | エンジン音、特定の周波数のロードノイズ | 逆位相の音でノイズを物理的に打ち消す | 騒音レベルの全体的な低減 |
参照元:音響学専門誌オンライン
レクサスNXのノイズ改善を実感できる静音DIYグッズ5選【まとめ】
レクサスNXの静音化は、高価なプロの施工に頼るだけでなく、適切なDIYグッズを使えば、ご自身の手で十分な効果を得ることができます。ここでは、私がプロの視点から選んだ、費用対効果が高く、特にNXのノイズ傾向に対して効果的な静音DIYグッズを5つ紹介します。
| グッズ名 | 用途 | 対策できるノイズ | 選び方のポイント |
| 高性能ブチルゴム系制振シート | ドア、フロア、ルーフのパネル | ロードノイズの共振、パネルからの透過音 | 厚すぎず、重量が抑えられた自動車専用品を選ぶ |
| 高密度遮音・吸音マット | フロアカーペット下、トランクルーム | 低周波のロードノイズ、排気音のこもり音 | 難燃性があり、裏面に滑り止め加工があるものを選ぶ |
| D型/P型ゴムモール | ドア、ボンネット、トランクリッドの隙間 | 高速走行時の風切り音、外部騒音の侵入 | 貼り付け面の幅に合ったサイズと、高い耐久性を持つものを選ぶ |
| タイヤハウス用吸音フェルトシート | タイヤハウス内側のインナーライナー裏 | タイヤからのパターンノイズ、水切り音、小石の跳ね上げ音 | 耐水性があり、熱に強い素材(グラスウール系は避ける)を選ぶ |
| ダッシュボード・バルクヘッド用遮音材 | ダッシュボード奥、足元周辺 | エンジン透過音、メカニカルノイズ | サイズが調整しやすく、高密度で遮音性能指数が高いものを選ぶ |
これらのグッズを、これまでに解説した「ノイズの発生源」に合わせて適切な場所に施工することで、レクサスNXの静粛性は劇的に向上します。静音化は、一度にすべてを完璧に行う必要はありません。
まずはロードノイズ対策としてタイヤハウスとフロアから着手し、次に風切り音対策としてウェザーストリップ強化、最後にエンジン音対策としてボンネット裏やダッシュパネルの施工、というように段階的に行うことをお勧めします。愛車のNXが持つ本来の上質な静粛性を取り戻し、より快適で質の高いドライブを楽しんでください。
【まとめ】
- ロードノイズ対策は、静音タイヤへの交換が最も効果的であり、根本的なノイズの発生を抑制できます。
- 低周波のこもり音(空洞共鳴音)は、タイヤハウスへの吸音材施工や高性能な制振材の活用で大幅に軽減できます。
- 高速走行時に発生する風切り音は、D型・P型ゴムモールを使ったウェザーストリップの強化が安価で高い効果をもたらします。
- エンジン音の侵入は、ボンネット裏の吸音と、難易度は高いが効果絶大なダッシュパネル裏への制振・遮音対策が中心となります。
- ハイブリッドモデルのモーター音は、フロアパネルや後部座席下のバッテリー周辺への制振・吸音材の追加で対策可能です。
- 雨天時のノイズは、タイヤハウス内のインナーライナーを吸音性の高い素材に交換することで大幅に軽減できます。
- 静音化DIYを行う際は、制振材の貼りすぎによる車両重量の増加と、内装の再取り付け時の不具合に注意しましょう。
- カーオーディオのイコライザー調整で、ノイズが集中する低周波(80Hz以下)や高周波(8kHz以上)を調整し、体感ノイズを和らげられます。
- ディーラーや専門業者によるプロの施工は、特にダッシュパネルやルーフなど、DIYが難しい箇所での確実な静粛性向上を求める場合に適しています。
- ご自身のNXの年式やグレード(F SPORTなど)のノイズ傾向を把握し、ロードノイズや風切り音など、最も気になるノイズから対策を始めることが成功の秘訣です。





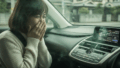

コメント